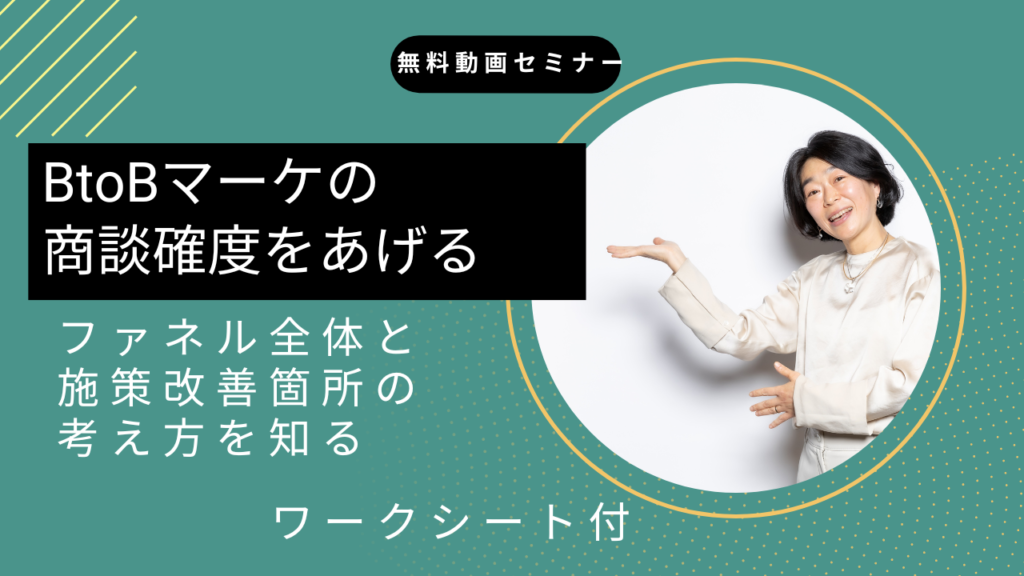売れる動画コースをつくるために、動画教材のカリキュラムをどうつくっていったらいいのかをお伝えします。
目次
動画は、視聴環境が自由な分、学ぶ難易度が高い媒体
動画教材のカリキュラム作成で、戸惑われるのは、アウトプットが初めてのクリエイターだけではありません。論文発表や、セミナー講師の経験がある専門家の先生も同じように、クリエイターになりたての時は右往左往されます。その理由は、動画が、「一定の視聴時間の拘束を求めるにもかかわらず、視聴を強制する力がない」媒体だからです。
テキスト媒体ならば、読み手は、決められた方向に向かって情報を受取る強制を受けません。
リアルのセミナーや教室受講生ならば、会場や教室に一定時間缶詰になるので、否が応でも参加者は最初から最後まで聞かざるをえません。
強制力がないなかで、最初から最後までを一定方向でずっとインプットしつづけなければならないつらさは、あなたも経験があるのではないでしょうか。
家族旅行の途中に資格取得のための勉強で動画視聴を想像するだけで、苦痛でしょう。
わたしたちオンラインコースクリエイターは、こんな強制力がない環境に居る受講生に配慮しなくてはなりません。
自分の意志で視聴をつづけてもらい、ゴールまでお連れすることができるように、教材動画をつくる必要があります。
それは、動画構成や編集のテクニックだけでなく、カリキュラムの組み立て方でも、大きく結果を左右することになります。
このことを逆からみれば、動画編集テクニックがなくても、カリキュラム構成がうまく創られていれば、受講生を飽きさせずゴールまでお連れすることも可能ともいえます。
用語確認
カリキュラム作成方法のご説明に入る前に、用語の意味や、何を指すのかということを確認しておきましょう。
わたしが、和田美香オンラインスクールのブログや教材で使用している用語は、ここでお伝えする意味で使っています。
スクール……動画コースが格納されている場所。テーマでまとめられている。ログイン管理はスクール単位で行う。
コース……1本の動画教材のこと。長さは30分から10時間越えまでさまざま。
カリキュラム……1本の動画教材の、章やレクチャーが並んだもの。動画教材の目次ともいえる。
セクション……カリキュラムのなかの章のこと。
レクチャー……章の中の、一つ一つの動画のこと。
カリキュラム作成前に決めたい3つの項目
カリキュラムに入る前に、3つ決めていただきたい項目があります。
- 届けたい理想の受講生はどんな人か?
- コース視聴し終わった受講生には、どのようなゴールまでお連れしたいのか? 理想の受講生に、受講後、どういう状態に変化していてもらいたいのか?
- 受講生が学ぶことは何か?
これを書き出してから、カリキュラム作成にすすみましょう。
ボリュームについてよくある質問
1本のコースのボリュームについて、よく質問を受けます。
なので、目安をお伝えします。
あくまでも目安なので、このとおりにしなければならない、ということはありません。
たとえば、和田あ初めてつくったコースは、全部あわせて8時間30分越えの、かなり長いものでした。
でも、あなたは、最初からこんなに長いものを、必ずしもつくる必要はありません。
コース全体時間……30分から2時間程度
1つのコースのなかのセクション数……5から9程度
1つのセクションのなかのレクチャー数……3から10程度
1つのレクチャー動画の尺の長さ……3から8分程度
もし、1つのセクションのなかにレクチャーが11以上にもなりそうなら、セクションを分けるようにしてみてください。
もし、1つのレクチャー動画の長さが10分を超えるようなら、レクチャーを分けるようにしてみてください。
1本のレクチャーの長さを短くしたい理由
1本のレクチャーを3から8分程度に収めていただきたい理由があります。
それは、視聴者が、「ながら」で聴いていることを前提とし、「ながら」でも学べる長さにしていただきたいからです。
電車に乗って通勤中に聴いていて、あと一駅だから、あともう1レクチャーだけ聞いておこうと、学びをすすめている受講生がいると想像してみてください。
家事の合間や、車通勤の間に、耳だけかたむけて、学んでいる受講生もいるでしょう。
少なくともわたしは、動画教材を購入したあと、机に座ってパソコンを開いて動画を視聴するというかたちはとっていません。
いつも、何かをしながらです。
「ながら」であれば、好きな時間に視聴し、まとまった時間がとれたら、学びの実践につかうことができます。
それと、1本1本の動画が短いことで、次へ進む感覚を受講生に得ていただくことができ、「自分は学びを進めることができている」という自己肯定感を手にしていただけます。
すると、次にまた学びを勧めたい、という気持になってもらいやすくなります。
もし、1本の動画が長くて、2~3日かけて「ながら」時間で視聴してもまだ視聴し終えないぐらいだと、達成感がなく、自己嫌悪におちいって、動画で学ぶということから遠ざかってしまいかねません。
せっかく、お金を払って手にしていただく動画教材です。
受講生の学びがつづくしかけを、カリキュラムからも提供したいですよね。
1本のレクチャー動画が長い講師の先生もおられるよ、とおっしゃるかたもおられるでしょう。
はい、受講生との関係性が構築できているミドルエンドやバックエンドの動画商品なら、その講師の話をもっと聴きたいという動機で講座を受講してくださる方にむけて話しますので、1本のレクチャーが長くなってもまあ大丈夫です。
でも、いまは、「初めて動画コースをつくる」あなたにむけてなので、Udemy、もしくは、フロントエンド商品や、リードマグネットとして、動画コースをつくることになるはずです。
こんなときは、ぜひ、1つづつのレクチャー動画を、短めにして作ってください。
セクション数はどうやって決めるか?
1つの動画コースのカリキュラムのなかに入れたい、セクション数の目安を上にあげました。
さあ、あなたも、あなたの動画コースのカリキュラムの「理想の受講生」「ゴール」「学ぶこと」を決めたので、次に、セクション数を決めましょう。
ここでは、エイっときめてしまうことをおすすめします。
まず、5つセクションをつくろう、とか、5か7か9で、セクション数をエイときめてみてください。
セクション名レクチャー名を書き出す
エイとセクションの数を決めましたね。
その次に、そのセクションのタイトルを考えましょう。
また、タイトルがなんとなく埋まったら、今度はそのなかに、どんなレクチャー項目を入れるか、レクチャータイトルの名前を書き込んでいきます。
専門用語を使わない
セクションやレクチャーにタイトルをつけるときに、専門用語を使わないでください。
専門用語ではなく、受講生さん、つまりあなたのお客様がいつもお話しになっている声から、単語を拾ってきてください。
例えば、先日、動物病院の先生が、セクション名に「診察の流れや処置と自宅練習前編」という長いタイトルを最初考えてこられました。
わたしはペットを飼っていないので門外漢ですが、でも「処置ってなんかちょっと怖い印象を文字から受け、やっぱり手術される前の大層なことなのかな」という、恐れる気持ちが生まれたことを、動物病院の先生に、正直に伝えました。
すると、飼い主さんは、いつもは「処置」という言葉ではなく、「先生に看てもらう」としか言わない、とおっしゃります。
であれば、セクションやレクチャーのタイトル、ひいては、コースタイトルにも「専門用語は使わず、いつも飼い主さんが使っておられる言葉にすべて変換してください」というお願いをしました。
動画コースをつくる先生方は、専門家の方が多いです。
だから、つい、自分目線で、伝えたい専門用語を羅列してしまいます。
でも、先ほどから繰り返すように、動画コースの受講生は、あなたの居ないところで、一人で、しかも、何か別のことをしながら視聴します。
「この動画を視聴すると、自分にとっていいことがある」と感じてもらえないと、動画視聴開始にさえならないことになりかねません。
動画視聴開始してもらえなかったら、ゴールへお連れすることが難しい、つまり、動画でお伝えする意義そのものがなくなり、動画の存在意義がなくなってしまうのです。
そんなことになりたくないですよね。
ということで、専門用語を書いてしまったら、お客様の使っている言葉に、あとから変換しておきましょう。
「専門用語を無意識にどうしても使ってしまう」方は、第三者にチェックしてもらるといいですね。
イントロダクションの章で何を語るか
イントロダクションの章で、何を入れたらいいですか?という質問もよくいただきます。
和田がいつもイントロダクションの章で入れている内容をお伝えします。
最低限この5つだけはいれてください。
・コースの対象
・コースのゴール
・コースで学ぶこと
・講師自己紹介
・受講のすすめ方
・受講の前提条件(あれば)
対象、ゴール、学ぶことは、カリキュラム作成前に決めた内容を、そのまま紹介するだけで大丈夫です。
「講師自己紹介」は、短めに、コースのテーマやタイトルに関するあなたの経験や経歴のみピックアップして語るだけにしてください。
あなたにすごく権威があるとか、すごい実績がバックグラウンドにあるとか、そんなことは、受講生には関係ないことです。学びを進めるために、適切な方から学んでいるんだということを感じ取ってもらえるだけでOK。
あなたに沢山の論文実績や、所属学会があったとしても、受講生の学びに直接かかわりのない経歴は削ってかまいません。
自己紹介動画が4分を超えるようだったら、削る要素があると考えて、みなおしてみてください。
「受講の前提条件」は、受講するために必要なモノや、知識レベルがあれば、案内しておきましょう。たとえば、「経営学の基礎はしっていると理解しやすいです」といった具合です。もし、前提条件がなければ、「受講のための前提条件は特にありません」と伝えておくのもいいでしょう。
セクション毎に決まったレクチャーを入れておく
カリキュラム作成時、セクションごとに、きまったタイトルのレクチャーを2つ、決まった場所に入れてください。
ひとつめは、「この章で学ぶこと」というタイトル。
置く場所は、セクションの冒頭です。
つまり、各章ともに、「この章で学ぶこと」というタイトルのレクチャーから始まります。
ふたつめは、「この章のまとめ」というタイトル。
置く場所は、セクションの末尾です。
つまり、各章ともに、「この章のまとめ」というタイトルで締めくくり、学んだことを振り返って総括してください。
どうして、このような決まった内容を挟むのか、その理由もお伝えします。
テキスト媒体は、真ん中を読んでいる途中でも、目次へさっと行き来が自在に、そして瞬時にできます。
一方、動画教材は、「いまは、全体のなかのどの部分を学んでいるのか」ということを確認するためには、動画をいったん止め、カリキュラム全体をみわたせるようにしなければなりません。
そこで、小さな目次のようなレクチャーや、まとめのレクチャーを入れることで、動画を「ながら」視聴しながらでも、「いま自分は何を学んでいるのか」「ここで学んだことは全体のなかでどんな位置で、次はなにを学ぶのか」をこまめに確認できるようになります。
これにより、受講生が学びを継続しやすくなるという利点があります。
また、「まとめ」があることで、「今日はよくがんばった、ここまでにしておこう」という区切りのきっかけにもなります。
脈絡のないところで視聴を追えてしまったら、「昨日まで何を聴いていたのだろうか」と、もいちど、いくつかレクチャーをたち戻って再確認してから進む必要がでてしまいます。
ちなみに和田の動画には、「まとめ」がないコースも多いです。
超初心者向けのコースでない場合は、わざと「まとめ」のレクチャーを省いています。
でも、理解を促すという点では、あったほうが親切だとわたしはいまでも思っていますので、ぜひあなたも最初はつけてみてください。
1セクションに1レクチャーでもいいですか?
「1セクションに1レクチャーでもいいですか?」という質問をいただきました。
結論からもうしあげます。
1セクションを1レクチャーに収めてしまうことは、おすすめしません。
きちんと、上でもご案内した「この章で学ぶこと」と「この章のまとめ」で、言いたいことをサンドイッチしてレクチャー構成をつくってください。
1セクションを1レクチャーでつくってしまう方の動画を拝見していると、たいてい、20分かそれ以上のものを創られます。これだけ長いものであれば、レクチャーのなかに、話題がいくつも入っていることになります。
話題毎に、1つのレクチャーに独立させてください。
Udemyも公式チュートリアルでも、1つのレクチャーは6分以内の動画が理想的と書かれています。
1つのレクチャーで、お伝えするテーマは、1つだけです。
もし、話題転換するとか、事例を増やしたいということであれば、それぞれ別のレクチャーに分割しましょう。
ちなみに、20分もの長いレクチャーを創って、「1セクションに1レクチャーでもいいですか」と聞いてこられたクリエイターさんは、都度短いレクチャーを保存し、編集する作業が面倒だったから、作業をパスしたかったそうです。
面倒なことは、やりましょうね。
受講生の学びの環境向上につながりますから。
1本のレクチャーが10分より長かったら切ったほうがいいですか?
こんな質問もいただきました。
「10分より長いレクチャー動画ができてしまいました。切って、2本に分けたほうがいいですか?」
はい。
短い分数に、分けてください。
YouTube動画の企画や制作に慣れている方は、一本の動画の分数が長くなる傾向があるのでしょうか。
レクチャーひとつが、1ステップを示すようにしましょう。
ステップ・バイ・ステップでゴール達成まで受講者に寄り添うように動画でお伝えするのが、動画コース制作の神髄です。
なので、1歩1歩を小さくします。
1歩1歩が小さいと、伝えている内容を実行しやすくなります。
小さな一歩は、簡単に終わりますよね。
長く難しい内容を、一度にドサっとお渡ししても、受講生が消化不良になってしまうだけです。
動画コースは、難しいノウハウをお伝えするための道具ではありません。
なので、1つのレクチャー動画が10分を超えるようになったら、何も知らない受講生からみて、その1歩は十分に小さいか、さらに2歩以上に分けられないのか、ぜひ再検討して、短く切ってください。
眠くさせたらクリエイターではないです
あなたも昔、教室で眠たくなって、机の上につっぷして眠ってしまったことありませんでしたか?
わたしは、高校時代、よく寝ていた記憶があります(だから成績もふるわかなった。苦笑)。
教室に缶詰めにされ、先生の話を聴くことを強制されている環境下にあれば、たとえ寝ていようと、先生の話しはすすんでいきます。
そして、終了チャイムとともに、お話しも終わっていきます。
高校は、それでも単位をもらえ、卒業できました。
でも、動画は、強制されて観るわけではありません。
わたしたち大人のための動画教材は、すべて受講生の自由意思で視聴がすすみます。
眠くなったら、大人の受講生は、そこで寝ていいのです。
動画コースを再開したくなかったら、再開しなくてもいいわけです。
でも、そうなると、わたしたちは、受講生をゴール達成までお連れすることはできません。
ゴール達成までお連れすることは、わたしたち動画コースをつくるクリエイターの責任になります。
わたしたちクリエイターは、受講生をゴールまでお連れするという責任を放棄してはなりません。
受講生が受講を継続してくれなかったら、受講生がゴール達成して繰らなかったら、クリエイターの存在意義がなくなってしまうからです。
眠たくなって途中で受講を止めても、また次、すっきりしたときに動画視聴を再開したくなるコースカリキュラムにしたいですよね。
あなたの、コースカリキュラム作成の工夫で、和田がここでお伝えしている以外で、新しい気付きをみつけられたら、ぜひ、メールかコメント欄で教えてください。
あなたのクリエイターとしての成功をお祈りしております。
ただ難しい、珍しい内容を伝える動画を創るだけでは、クリエイターでは、ないのです。