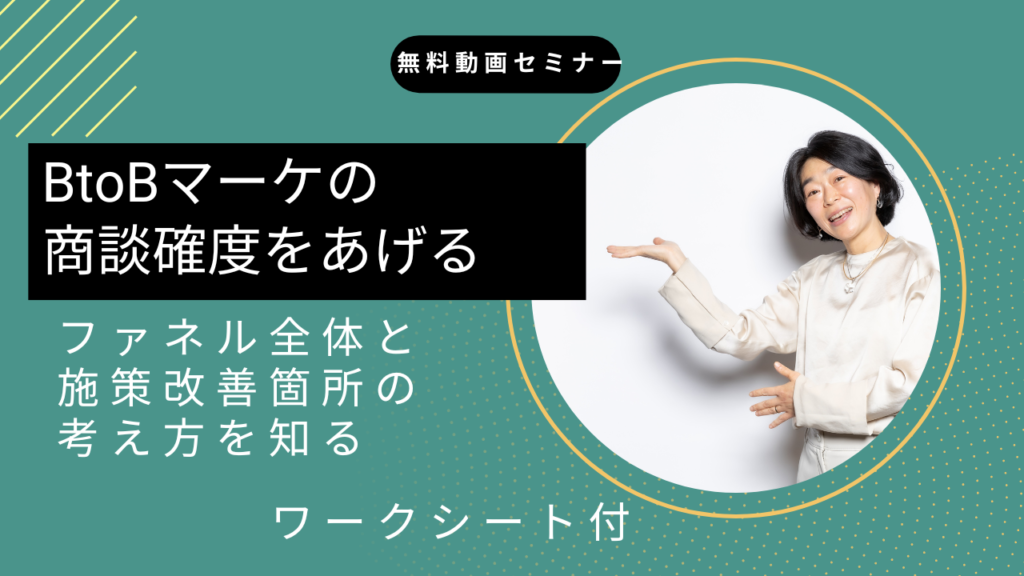目次
1、いつ価格を上げるか?
あなたは、商売を始められて以降、価格以上の価値を提供されてきたから、ここまで商売をつづけておられます。
自分の手でゼロからここまでの道を築いてこられたこのこと自体、とてもすごいことです。
価値提供をずっと約束しつづけてここまでこられ、支持してくださる方がおられるのですから。
でも、あなたはいま、いまのままではお客様への価値提供をこれ以上自分の手だけでは引き上げられないと感じています。
仕事の時間が24時間以上に増えるわけでもなく、さらなる価値を提供するにも人手がさらに必要で、そこをなんとか乗り越えなければ、と考えはじめています。
そんな「キャパオーパー」のとき、価格を見直すタイミングになります。
価格を見直すと、お客様がはなれていっていまう心配もチラとあなたの頭のなかをよぎるなかなかふみきれないときがあるかもしれません。
でも大丈夫。
価格を見直す方法はたくさんあり、ビジョンや現場の現状にあわせてすぐに実行しやすいものから、資金が必要なものまであります。
このブログでは、メリットとデメリット、予測できる変化、やり方、準備、エピソードを順を追っておつたえします。
2、値上げのメリット・デメリット
時間的制約や物理的制約が出てキャパオーバーになったときが、値上げのタイミングです。
価格を「顧客が感じる価値への感謝の尺度」という観点からみると、値上げのメリット・デメリットは分かりやすいです。
値上げのメリット
値上げのメリットを先にお伝えしましょう。
値上げするということは、顧客に対し、提供価値向上を約束するということになります。
顧客側にとって利便性向上、時間短縮、利益増大にむすびつくものとなります。
そして、価値向上を約束した内容を信じて下さる方とは、関係性強化につながります。
なので、これまでただの顧客との関係だったかたが、ファンとして接してくださるようになってゆき、仕事がやりやすくなるというメリットも、提供側にあります。
提供価値向上を約束するということは、より提供内容にトンガリをもたせることが前提にもなります。
あれもこれも、すべての面において素晴らしいということを目指していたとしても、「結局なにがよくなったの?」という印象を与えかねません。
提供価値が向上するポイントに賛同いただけるように、価値向上ポイントを明確に示す必要があります。
となると、結果的に、価値向上ポイントに期待して下さるかただけが残ることになります。
つまり、顧客選別につながります。
ひいては、物理的制約や時間的制約があったとしても、効率化、利益拡大につなげやすくなります。
価格アップは、ただサービス(商品)提供者側の利益増大だけに視点がゆくと、横柄にみえますが、実は、ベストなタイミングで価格アップを行うことは、顧客にも、サービス提供者がわにも、両者に得なことが起こるわけです。
せっかく自分主体で活きる道を選んだ起業なのに、経営者になってからも嫌いな顧客と「お金もらってるのだから」といやいや築く関係は、自分だけでなく相手も、時間ももったいないだけでなく、パフォーマンスも落ちて、両者の得になりません。
まれに、「価格アップをすると、『もっとあれもこれもやってくれ』と顧客がよりわがままになり、これ以上対応しきれなくなる」と心配される経営者さんもいらっしゃりますが、逆です。
顧客側も、どんな点を期待していいかわからないから、「価格が高いなら、こんなこともしてくれるのかな、あんなこともしてくれるのかな」と妄想をふくらませなければならない状況におちいっているだけなのです。
きちんと順をおって価格をアップを提示すれば、そんな心配は要りません。
値上げのデメリット
値上げのデメリットは、値上げのメリットの反対になります。
顧客のある一定数が、来店頻度、利用頻度を下げます。
価格をアップすると、低価格サービス(商品)をもとめる顧客がはなれていってしまうことは避けられません。
3、顧客が減るという経営者の不安をどう解消するか
「顧客数が減ると売上も減る、利益も減るのでは」と不安にかられる気持ちにただ踊らされると、価格アップにふみきれません。
ではどうするか。
答えは、最悪の想定をすることです。
価格アップを成功させたかたの、共通点みてみましょう。
価格アップを結果として成功させているかたは、価格アップのデメリットをきちんとリスクとして計算し受け入れたうえで実行されていました。
つまり、「最悪どうなるか」ということをきちんと受け入れて、腹をくくって実行されています。
「最悪」の数値が見えていれば、怖さも半減します。
いまの自分と、最悪な場合との差が、具体的にわかるからです。
具体的に数字で差が見えると、打つ手も、より具体的になります。
もしあなたが価格アップが怖くても怖くなくても、まずは「最悪」の想定してみてください。
「最悪」数値を見える化する手順
まず、予想損益をだしてみましょう。
売上計算は、客単価×客数で簡便に計算していただいて構いません。
客単価は、「価格アップ後に期待する客単価」を。
客数は、「価格アップした後に、最悪減ってしまったあとのこってくれる客数」を。
これで「最悪の売上」がでますね。
そして「最悪の売上」から、必要経費を引いてみてください。
これで、「最悪の営業利益」がでます。
現状の営業利益とくらべてみてください。
差がみえますね。
やってゆけると腹をくくれる数値ですか?
大抵の場合、上昇思考で価格アップを図るので、「最悪の場合を想定」したって無駄、わたしはぜったい最悪にはしない!、 絶対、理想の数値に近づかせる!
そうあなた、おもってますね。
はい。
「最悪の想定」になったときにも、死なないことがわかったら、怖くないですよね。
打つ手がある間は、死にません。
この、今と、最悪の間の数値を常に頭におきながら、最善の手をうっていきましょう。
4、値上げの前の準備
社長のあなたが背中をみせて頑張って来たなかで、ありがたいけれど、ずっとただ忙しい。
スタッフもただ忙しい。そんな状況を打開しようと、価格アップを目指そうと決めたとしたら、まず何をすべきか。
4-1 働くがわの環境を整える
値上げの前にしなければならないことには、3つあります。
なによりもまず最初に、理念の浸透です。
そして次に、労働環境の整備です。
それがおわってから、最後に、価格アップの実行です。
どうして、一番最初に、ミッションとビジョンを言葉で明確にし、スタッフと共にチーム全体に理念浸透をはかることがくるか?
それは,2つの理由があります。
ひとつめの理由。
価格アップが従業員の労働環境を好転させ、人生の満足度を上げるためが第一義であることを知らせることがなによりもまず必要だからです。
価格アップを前向きに、全ての一員が、自分のこととして受け入れる土台が必要だからです。
これまでもそうですが、これからはなお、あなたひとりではなく、スタッフもふくめ、チーム全体で商品やサービスを提供することになります。
価格価値を提供するのは、あなたから直接ではなくなってゆきます。
あなたと想いを同じくする従業員のみなさんひとりひとりが顧客との直接の接点となり、商品そのもの、サービスそのものを形成します。
だから、もしチラリとでも「経営者が自己満足で価格をあげてて、自分達にはなんの関係もない」と感じていたら、価格にみあった価値提供を徹底することができません。
「なんのために価格をあげるか。それは、わたしたちの質をあげることで、より高い顧客満足をうみだすため」という、道理をきちんと腹落ちするよう、文字で示し、話してしめしてゆく必要があります。
背中をみせて走って来た社長さん、どうして価格アップをするかということを浸透させる時間をつくることが大切です。
ここ、わすれないでくださいね。
結構軽く考えて突っ走ってしまわれる社長さんが多いのが事実です。
価格アップは、理念をチームでしっかり共有するチャンスです。
理念浸透をいままではかっていなかったとしても、いいチャンスととらえてここでやりましょう。
理念浸透がまず最初にくる、二つ目の理由。
もうひとつは、価格アップをはじめとする労働環境の変化についてゆけなくなる方にも、準備期間をもうけることができるからです。
価格アップが、「労働環境を好転させ、人生の満足度を上げるため」と伝えられても、どうしても変化は嫌という方もなかには必ずいらっしゃります。
従業員全員のこらず賛同してほしいと思う気持ちが社長のあなたにあったとしても、変化に対する温度差は避けがたいものです。
顧客との直接の接点である従業員のなかに、方向性が違う方がいらしゃると、価格にみあった価値提供の約束が難しくなるので、変化を嫌う方がチームからはなれてゆくことはやむなしとかんがえてください。
変化を嫌う人もいます。無理して一緒にいても互いに無理が重なるだけです。
変化がおこるときには、チームの入れ替えが必ずあります。
来るべき環境の変化を、社長のあなたも、そして従業員のひとりひとりも、自分のこととしてうけいれてゆく心の準備をする段階でもあるのです。
4-2 労働環境の整備
値上げで、労働環境は変わります。どう変わる?
価格アップによって、どんなよいことが働く側で起こると、伝えられますか?
- 仕事がたのしくなる
- 仕事に余裕ができる
- 仕事に専念できる
- 顧客から喜びの声が増え、さらに励みになる
など
あなたの事業では、価格アップが従業員の働くことへの満足度をあげ、人生の質を上げることに寄与する仕組みづくり、環境づくりをどう具体にしますか?
働く者にとって、価格アップで得られるお金は、自分に具体的にどうまわってくるの関心が高いです。
それぞれの職場にとって、従業員満足が高まる方法や、現状の課題解決に直結する方法はちがってきます。
いつくも手段があるなかで、大きくわけて2つの方向があります。
あなたの事業では、どちらの方向をとるほうが、いまの課題解決に近くなるかという基準でえらんでください。
スキルアップの方向
従業員の能力を高めることにより、顧客の満足度が直接的にアップします。
高めるスキルは、技術だけにとどまりません。
メールの使い方、ブログの書き方など、顧客との接点をより良質にし、顧客から支持を高くえてゆくための方向もあります。
また、業務全体をみわたす視点をもつためのチームビルディングのための研修費用や、福利厚生に使うことも考えられますね。
理想のサービス(商品)提供環境になってゆくために必要なスキルや段階を、年間計画とキャリアデベロップメント計画にもりこんでゆくと、漏れがなく、むりなくすすめられます。
権限委譲の方向
権限委譲にも、お金が必要です。
責任だけあって、お金のことはいつも経営者にお伺いをたてなければならないというのでは、権限をもっているとはいえません。
とくに接客業の現場で、即座に判断できるかどうか顧客満足度に大きく影響を及ぼします。
たとえば、「お客様の誕生日ということが今日ご来店時にわかったので、花束とカードをおかえりの際に準備してさしあげたい」と現場のひとりが考えたとき、それをすぐに実行にうつせるだけの判断権限と金額の上限を最初にきめておけば、顧客満足度向上にすぐ結び付けられます。
ここでは、どんな権限を委譲するか、そのための予算をどれぐらいつけるか、きめておくことではじめられます。
以上が2つの方向でした。
価格をアップして得られる利益はただ経営者の取り分にまわるだけだとおもっているスタッフもいます。
お金の流れが、「従業員満足度をまずさきに高めることで、顧客満足につなげ、ひいてはそれが働きがい」になることを、うまく伝えたいですね。
5、値上げの方法
値付けは経営といいます。
なので、値上げの方法についても、いろんな事例を集めると、ほんと奥深いです。
価格と商品(=サービス)内容について、日々考えるのが好きでないと、経営者はつとまらないのではないかと思うぐらいです。
5-1 値引きを辞める
利益率をあげるために顧客単価を上げる手段は、いまあるメニュー表の数字を、さらに高い数字に取り換えるだけではありません。
いま行っているすべての割引を見直すことも、値上げのひとつです。
あなたのビジネスで、顧客との接点のどこかで割引してませんか?
新規顧客獲得の値引き
たとえば、美容室でよくあるのは、新規客を集めるために「初回50%引き」といった、新規顧客への割引サービス。
新規顧客に来店メリットを感じていただくために、「割引しか思いつかない」とおっしゃる場合もおおくおられます。
ですが、割引だけが顧客誘因の武器ではありません。
価格以外のよさがわからないから、「割引でもしているところに、とにかくいってみるか」ぐらいの気持ちでしか顧客はないのです。
なので、新規客から2回目客になるリピート率は、割引をせずに新規集客している店舗とくらべ、低くなります。
割引せずに新規客を集客する方法さがしてみる勇気をまずもってください。
新規集客の方法は、たくさんあります。
リピート客への割引
リピート客になってほしいからと、既存顧客に対して、「次回割引ク―ポン」などくばっていませんか?
員カードと称してポイントを顧客に付与し、ポイントがたまったら割引クーポンをだしたりしてませんか?
リピートくださるかたに割引クーポンを発行すると有効なのは、生活用品など買い物頻度が高く、来店頻度をおおくしてほしい物販店舗です。
クーポンを発行する事で、余計な買い物をしてくださったり、クーポンを使おうと来店間隔を短くしてくださることにつながり、結果一人当たりの顧客がつかってくださる金額が増えるわけです。
ですが、業種によっては、同じ店舗経営でも来店頻度にの違いから向いていない店舗もあります。
「女性はクーポンを貯めるがすきだから」という感覚だけで、割引クーポンを発行しても有効でない、むしろ利益率を圧迫するだけという場合もあります。
なので、リピート対策に割引がほんとうに有効かどうか、みなおすことも有効です。
5-2 、サービス提供時間を伸び縮みさせる
サービスの提供時間に注目し、価格アップする方法をみてみましょう。
たとえば、いままで5千円のサービスを標準時間60分で提供していたといします。
鍵は、時間を伸び縮みさせてみることです。
時間を縮めてみる
サービス内容は同じで、ただ、提供時間を短くし、時間単価を上げる方法がありますね。
たとえば、標準時間を50分にしてみる、標準時間を30分にしてみる、でも、価格はいままでどおり5千円。
サービスの時間を短くするとき、短くする理由を顧客にしっかり説明してくださいね。
また、サービス提供者である現場スタッフ全員の技術力強化をおこなう必要もあるでしょう。
あのひとからは、30分、このひとからは60分かかって提供するということでは、顧客体験が違ってくるからです。
なんでも、ゆっくり、ゆったりが好きな顧客ばかりとは限りません。
いままで、1時間かかっていたものが、30分で済ませられるなら、喜んで時短分の値上げをうけいれてくださるでしょう。
「時間短縮」も、大切なお客様サービスのひとつです。
時間を延ばしてみる
サービス提供内容を濃くするなでど、提供時間を長くし、価格をあげる方法です。
この場合、時間単価を下げずに、長くした時間分の単価をうわのせできるかどうかがカギです。
時間単価がさがってしまったら、価格アップの意味がなくなってしまいます。
たとえば、いままで90分のお稽古で1万5千円いただいていたとします。
そこに、先生とのお茶の時間を30分とることもいっしょにして120分にし、2万円の講座価格にするといった具合です。
サービスの抱き合わせ販売、セット販売と考えは同じです。
時短と延長セットと、どちらがいいか?
それは、あなたの顧客は、どちらをよろこぶ方が多いかで決めて下さい。
5-3 業界標準の無料を見える化する
あなたの業界で、「業界ではあたりまえとして顧客に提供しているけれど、作業時間費用や材料費等がかかっていて、ほんとうは有料化したい」という部分ありませんか?
例 美容業
カラーやパーマの薬液塗布のまえに、頭皮を保護するこころづかいでスプレー式のトリートメントをかならず使ってくださる美容室さんがありました。
でも、頭皮保護のトリートメントが、カラーやパーマの施術に含まれていることを、このお店さんではまったく顧客に知らせていませんでした。
2つの理由からです。
ひとつは、スプレー式のトリートメントで、やったかやらなかったか、わかりにくいと施術側が感じておられたため。
もうひとつは、美容室ならこの工程をいれるのは当たり前でしょ、と考えておられたため。
世の中には、頭皮が傷むから、頻繁なカラーやパーマをしたくないと考えている方も多いとことをサロンオーナーさまにお伝えしました。
こちらは、改装後の価格見直しの際に、頭皮保護のトリートメントを含んだセット価格に料金改定されました。
顧客サービスと、無料サービスは違います。
顧客に価値を感じてもらえれば、無料でなくてもかまわないわけです。
無料だからと言って、なにも伝えないと、そのサービスは、ほんとになんにもなかったものになってしまいます。
あなた自身が、あなたの価値をゼロにしているに等しくなります。
そんなこと、あなたの業界でもありませんか?
例 設計
日本の慣行では、設計事務所で、受注前、平面図だけでなく3Dの完成イメージ画像までの無料提案は当たり前です。
でも、これ、コンサルティングを含む提案もはいっているので、設計の作業には大きな人件費がかかっています。
日本の設計事務所や工務店は、無料で書いた平面図の制作費用は、受注した方に、受注しなかった分の営業費用もすべて上乗せしています。
そもそも受注前の無料提案をやめれば、設計事務所も時間単価アップをはかりやすくなるし、お客様も無駄な費用をはらわなくていいという、両方にお得がでるとおもいますよね。
ちなみに、わが社でも、店舗設計サービスは、契約後にしか測量や図面作成作業にはいらないようにしていますので、明朗会計と喜ばれています。
業界標準に挑戦するときは、顧客のもっている「当たり前感覚」にも「そうかあ、おかしいんだあ」と気づいてもらうステップがあれば、「あなたのところだけ、なぜ有料、他社は無料なのに?」と理不尽ないわれかたをすることもなくなります。
顧客を育てるマーケティング活動が、大切な要素になります。
5-4、 時間単価を計算する
顧客の側が、高い安いをどう感じるかを考える前に、自分目線で一度現状を整理しておきましょう。
「自分が身体をうごかしてお金をいただくサービス」の場合は、特に、この視点を抜かさないでください。
自分が身体をうごかしてお金をいただくサービス業の場合、目先の売上アップを目指さないでください。
身体をうごかしてお金をいただくサービス業、たとえば、美容師、コンサル業、講師業、デザイナーなどは、自分の身体を動かすといっても、自分の時間は24時間しかなく、時間のキャパシティー増やすには、人手を増やすことでしか売上アップができない職業です。
なので、絶対にしてはいけないのは、売上アップをねらった値下げです。
値下げで一時的に顧客数が増え、売上が増えたとしても、24時間の壁につきあたるだけで、自分が疲弊し、長期の利益アップにはつながりません。
なので、まず、時間単価のアップを図って、売上アップを図ってください。
くれぐれも、割引して、たくさんの顧客をこなそうと考えないように。
あなたの今の時給はいくら?
開業当初は、おそらく、業界の相場や地域相場をもとになんとなくで価格決定したのではないでしょうか。
いまの、お一人当たりの時間単価はいくらですか?
たとえば、美容業で、標準作業時間60分のカット料金が4,000円の美容室だったとしましょう。
スタイリストとアシスタントのお2人で、カットとシャンプーをそれぞれ担当されているとしたら、乱暴な計算ですが、おひとりづつの時間単価を均すと2,000円になります。
理想の時給はいくら?
理想の、「稼ぎたい目標年収を」をまず挙げてみてください。
たとえば、いま夫婦二人で営業の個人経営の美容室を想定してみましょう。
月間、お2人で力をあわせ、200万円の売上をめざされているとします。
乱暴に計算すると、お一人100万円の売上ですね。
1カ月の営業日数は25日(隔週 週休2日)とし、労働時間は1日8時間(10時開店~18時閉店)とします。
するとお一人の時給単価が5,000円とでます。
60分が標準作業時間のカット料金が4,000円のメニューだったとしたら、時給5,000円をしたまわっていますね。
どれぐらい価格アップをすればいいかの目安は、いまの時給と理想の時給の比較で、検討がつきやすくなりましたね。
6 価格アップの理由をどう伝えるか
素材の高等を値上げ理由にあげるお店やご商売があります。
気持ちはわかります。
顧客としては、どうですか?納得しますか?
経営を、外的環境のせいだけにしてませんか?
顧客に提供するものはこのレベルを目指している、顧客満足はこの高さで提供したい、だから、この素材でないとダメなので、理解ください。
など、そんな「わたし」の視点も、ぜひ加えていただきたいなといつも感じます。
価格アップの方法が決まったら、あとは、顧客にどう伝えるかというだけです。
ここは、「自分で考えて下さい」とほんとはいいたいところです。
楽して、価格アップはできないからです。
でも、よく質問いただくところなので、価格アップの理由の例の一部を、お伝えしましょう。
6-1 ストレートに伝える
正直に、顧客に伝える方法でいいです。
「将来的に自分の価値を高め、より多くの貢献をしてゆきたいから、自分をもっと高め、より多くの価値提供をしていきたいから価格アップを決断しました」
どうです?
こんなに簡単、と驚かれましたか?
シンプルに、ただ値上げの理由を伝えるだけです。
嘘もごまかしも、まったくありません。
建前も、へたくれもありません。
ただ自分に正直になって、なりたい自分にむかって強い意志をもつだけです。
できそうですよね。
6-2 段階を設ける
価格アップしたい額が、いまとかなりかけはなれている場合、スムーズにすすめるために、段階をもうけて価格アップをすることもおすすめです。
価格を、理想の段階まで一気に上げす、3年ほどかけて20%づつ3段階かけてアップします。
20%アップするごとに、上記理由を繰り返しつたえてゆきます。
これなら、一気に顧客がいなくなる心配ありません。
7 価格アップしたら何が起こるか?
新しい自分にみあった顧客がくるだけ
価格をアップを実行すると、大抵、顧客は、入れ変わるものです。
優良顧客でこのかたはずっとわたしを慕ってくれていると、こちらが一方的におもっている方も、価格アップについてきていただけない場合があります。
逆に、その価格でお世話になりたいと新規の方がすんなりいらっしゃります。
価格アップするときは、強い意思でなりたい方向を決めていますから、あいまいだったときの自分からはなれてゆかれる方もいらっしゃれば、あたらしいビジョンに共感してくださる方がでるのは当然なのです。
だから、特別すごい理由がなくても、覚悟したそのままの内容をストレートに伝えること、まずは検討してください。
この方法は、自分自身がサービスの時間と技術を提供している職業で、特にやってきていただいたことです。
クリニックでも、美容室でも、コンサルタントでも、設計士でも、コーチでも、やっていただけます。
価格アップを強い意志で決めると、自分で自分の顧客をさらに選ぶことにつながります。
8 事例
具体的に価格アップを実行された例をみてみましょう。
容室
月間の店舗営業日数を減らし、かつ料金も値上げされた美容室です。
ご夫婦で独立開業され、スタッフさんを2~3名雇用されている美容室でした。
3人目のお子様の出産を期に、完全週休2日の営業に踏み切られました。
保育園が休みの曜日は、奥様がスタイリストとして出勤できないため人手不足が生じます。
であればいっそ日曜日も、いままでの火曜日定休にプラスして休業日を増やし、スタッ
フの完全週休2日もあわせて実現させようというお考えでした。
それまでも、シフト制で完全週休2日を実現おられましたが、日曜日も含めて完全週休2日にふみきる美容室店舗は、なかなかいらっしゃらなかったです。
営業日数を削ると、売上が減ることについて恐怖の気持ちがでてしまうから。
また、日曜日が稼ぎ時という業界の通例から、なかなか思考が逃れられないからです。
正しい判断ばかりをもとめて怖がって決断しないのと、結果を生み出す決意をして行動を始めるのでは、大きな差が生まれますね。
でも、ここの経営者さんはちがいました。
いまこそ生産性をあげなければ、とお考えになっていました。
スタッフに、社会保険の加入も完備した労働環境をととのえてやりたい。
それに、サロンの現場教育以外に、デザイナーとして遊んで自分を高める時間ももってほしい、そう熱く語っておられました。
休日を増やす分、1日の売り上げを伸ばせばいいだけです。
ここで取られた戦術は、メニューのパッケージ化です。
コースメニューしか置かないというようにしたのです。
もともと、カット技術の幅がひろく、高単価カットメニューがある美容室さんでした。
どのコースにも、高単価カットメニューを組み込み、無料サービスの見える化をおこないました。
これにより、既存顧客に対しても、新しいパッケージメニューは従来からのサロンコンセプトをより強化し、料金をわかりやすくしたものだということを納得いただけました。
メニュー表を替え、価格アップした後も、9割もの既存顧客がのこってくださりました。
いまは、個人事業経営から、株式会社組織へと経営形態をかえられ、スタッフの社会保険も整備されています。
この店舗の価格アップの勝因は、「美容室が目指すもの」つまり、サロンの使命とビジョンを、開業当初からきちんと顧客と共有されていたことにあるとわたしは考えています。
サロンの目指すものを共有してくださる顧客づくりをしていたおかげで、メニュー表が大幅にかわっても、それは顧客のためにわかりやすくしたと受け止めてもらえたからです。
価格アップは、経営の小手先のテクニックではなく、使命(ミッション)をもって、ビジョンを実現してゆくためのひとつの過程として取り組めば、必ずうまくゆくと自信をもたせてくださった例のひとつです。
9 フラグシップブランドをつくる
顧客対象を変えずに価格だけをアップさせることを考えがちですが、実は、価格をあげることは、顧客を変えることにほかならないともいえるでしょう。
大きな企業が、価格帯別のブランドをつくったり、超高級なフラグシップブランドを育てたりするのは、1人の顧客を移動させるというよりは、別の顧客をとりいれることができるからです。
なので、価格を上げることを考えるなら、あなたの顧客対象は、どんなひとか、その顧客にどんな効果をもたらす商品(サービスなのか)を改めて問い直し、組み立てなおす作業が避けられず、ブランドを着替える、商品の名まえを変えるぐらいの、改変がそこにあっていいのです。
いまの延長線上で、価格アップが難しければ、ブランドを別にして、脱皮してください。
10、参考書籍紹介
高価格化についてお伝えいる中で、とっても共感する本があったのてご紹介します。
10-1 『絶対儲かる「値上げ」のしくみ、教えます』
石原明著
共感した点はが2つあり、ぜひ紹介したいと思いました
共感点の1つは、
『値上げの最大の目的は「時間」をつくること』とおっしゃっている点です。
経営者が、現場からはなれることができ、それゆえ、未来の売り上げを生むための仕組みづくりに時間をさけるようになる。
今日の行動が、今日の売り上げをつくると同時に未来を創る努力にもなると。
経営者のあなたに、たどり着きたいビジョンはあるけれど、ただ毎日仕事をこなすだけの日々で苦しいという思いがあれば、この石原さんの言葉は、同じようにひびきませんか。
ビジョンを達成させるために、いまのままでいいのか?
もっとワクワクをみなで共有するためにはどうしたらいいか?
そう考えているなら、「値上げをやるしかない」とたどりつける本です。
もうひとつの共感ポイント。
それは、値上げの方法はいたってシンプルだということです。
わたしは、「まず理念を伝え浸透させる」と値上げの方法の第一ステップを伝えました。
石原さんも、「いままでの経営は、ただ説明の言葉がたりなかっただけ。だからまず値上げすればいい。どう説明するかを考えればいい」と説いています。
たいていは、商品機能を上げるとか、そのために設備投資するとか、店舗改装するとか、大きな元手となる資金が必要だという思考のながれになってしまいがちです。
そうではなく、伝えていないことをただ伝えるだけという視点も、「いますぐ値上げをやる」ための後押しになりますよね。
説明だけで値上げをしてゆのを、自社にあてはめたらどうなるか、を考えるきっかけになります。
この本は、既存顧客をうしなったらどうしようか、とか、値上げしたいけれど踏み切れない経営者に、勇気をくれる本です。
つい最近、「慣れた方法を変えるのがスタッフが嫌がるから」という理由で、値上げのチャンスをふいにされた経営者様がいらっしゃりました。
怖かったのですね。
値上げで顧客がはなれるのではという恐怖の言葉を、払拭できなかったのですね。
10-2 『ザ・プロフィット 利益はどのようにして生まれるのか』
自分のビジネスや業界からはなれていただき、世の中にある収益を生む源泉のなかで自分はどこに位置しているのか、を俯瞰してみる視点をもっていただくための書籍をご紹介します。
エイドリアン・スライヴォツキー著
邦訳2002年出版
この本は、収益の源泉を23のパターンで示している、ビジネスモデルについての名著です。
大規模な製造業の企業が、過去儲けてきたビジネスモデルを分類しているだけ、ともしかして感じられるかもしれません。
それでも、サービス業や中小企業の経営者にも、わたしがこの本をおすすめしたいのは、そもそも値上げを考える根本に、収益をあげたいという考えがあわたしたちの視点をひろげてくれるからです。
その収益は、どんな仕組みで成り立っているのかを、ビジネスモデルはみせてくれます。
ビジネスモデルはは、立地や、商品や、店舗の外装や、広告などといったレベルとは違う、一段上にあります。
ビジネスモデルをたとえていうなら、顧客からいただいたお金が最大限利益につながる海はどこかを、高台から探す視点です。
この本からは、いま自分たちが立つ業界の儲けのしくみ以外に、どんな儲け方があるのか、他業界の儲けのしくみをみわたせます。
世の中にはは、顧客からお金をいただくポイントはこんなにたくさんある、ということを、まず23のパターンをみわたしながら、ご自分の生活体験からふりかえりつつ実感していただけるのです。
他の儲けのパターンにふれると、いまの自分の収益を上昇させるのは、もしかしてただ値上げするだけでなく、顧客からお金をいただくパターンを変えることでも実現するな、という道にたどりついていただきやすくなります。
下から見たあげた風景と上から見下ろす風景が違って見えるように、ビジネスも、見る視点の位置により見え方がかわります
顧客からお金をいただくパターンを考え直すきっかけの読書にするために,本書を読むとき、次の2つの質問してみてください。
(1)いまの自分の業界があてはまるのはどのパターン?
自分がいまおこなっている事業の立ち位置が、俯瞰すると、よくみえます。
古典的な儲け方だなあとか、お、結構新しい儲け方してるな、とか。
大抵は、業界の商習慣にのっとって収益パターンは決定されています。
あなたのところは、この23パターンのなかでは、どれにあたりますか?
それとも、あてはまりませんか?
わたしの考えでは、サービス業は、売り切り1回の古典的な儲けのしくみのところと、儲けどころをいくつもパターンをもっているところがあり、そのなかで規模が小さいほど、古典的な儲けのしくみのみでまわっている企業や事業所が多いです。
(2)あなたが「いいなあ」とおもった理想の儲けパターンはどれ?
もうひとつの質問です。
読んでいると、ちくしょー、この業界おいしいなあ! と感じられるパターンにきっと出会うとおもいます。
その理想に見えるパターンに、自分の提供するサービスをあてはめてお金をいただくことができるようになるにはどうしたらいいか、考えてみましょう。
この作業をすると、あたらしいメニューが、わんさか出てきますよ。
たとえば、あなたが美容室なら、「スイッチボード利益モデル」を読んだとき、シャンプーソムリエのサービスをおもいつくかもしれません。
ただ、これが、ディーラーをおこらせたり、顧客にとって選択の楽しみを奪うよけいなおせっかいになったり、思いつきが実際に利益を生むいいサービスではないかもしれません。
でも、顧客から利益をいただくポイントは、いまの自分のやりかただけではないという視点がうまれたら、新しいポイントを探したくなるのは止められません。
「物理学が物理のエネルギーについておしえてくれるように、利益は経済のエネルギーを教えてくれる。利益がないということはエネルギーがないということだ。未来を戦う能力もなければ、未来を作り上げる能力もないということだ。収益性を追求することは、高い利益はどこでどのように発生するかを常にといかけながら、考える日々変えてゆくことなんだ。
『利益はどこでどのように発生するか?』と5回問うてみる。5回目になってようやく答えに少し近づくことができるだろう。」
いまの儲けのパターン以外にもっといいパターンを見つけるきっかけになる、とおもったら、経営者のあなたなら、読まずにいられない本ですよね。
わたしは、この本、「ずっと置いておきたい本」のひとつにしています。
10-3『価格の心理学 なぜ、カフェのコーヒーは「高い」と思わないのか?』
行動経済学に影響をうけ、顧客の心理から価格を設定することを説いた本です。
リー・コールドウェル著
価格の心理学 なぜ、カフェのコーヒーは「高い」と思わないのか?
こんな方に向いてます。
業界標準の価格設定や、原価積み上げ方式の価格設定から抜け出したかた。
行動経済学を、具体的に自社の価格設定に生かしたいかた。
おすすめポイントは2つ。
(1)とにかく、比較、比較、比較
顧客に、ときにかく比較させることを主に3つの方向から指南してくれています。
1、顧客がうける価値の比較
2、競合との比較
3、おとりの自社商品との比較
自社商品の位置づけを変え、比較対象を代えてもらい、顧客の心のハードルを下げようというわけです。
上記3つのポイントは、章ごとにばらばらに書かれています。
もしあなたが著者の説く比較を自社の価格設定に取り入れたいなら、章ごとにばらばらに考えるのではなく、 1章と7章、9章、すべて満たす商品構成をまず考えてみると、比較の威力がわかりやすいです。
顧客のこころの中の何と比較させるかで価格が変わる例は、わかりやすいで。
(2)ワークする表が丁寧
おすすめポイントの2つ目は、とにかく親切という点です。
「商品の説明をただ変えるだけ」で、価格アップが実現するのが実感できるようにワークシートが巻末についています。
また、そのワークシートで考えた商品構成や価格が適正かどうかチェックする項目も丁寧についてます。
価格アップを指南する和田のコンサルティングは不要という本です。
10-4『良い値決め 悪い値決め ―きちんと儲けるためのプライシング戦略』
プライシングには、固定費と変動費の費用分解の知識が必要です。
ですが、顧客心理を考えているときにいきなり、費用の分類がでてきたとしても、数字が苦手な場合は、唐突に感じることとおもいます。
どうして費用をそもそもそ変動費と固定費にわけなくてはいけないのか?
これは、マネしていい考えか、どうか?
そもそも、自分に役立つ情報か?
そこで、「人間そのものが商売するサービス業」の方に、「費用構造がわかる本」をここではご紹介します。
「自分の手足をつかって稼ぐサービス業」には、美容師、整体師、コンサルタント、デザイナー、税理士、社会保険労務士、コーチなどの職業のかたが含まれます。
田中靖治著
良い値決め 悪い値決め ―きちんと儲けるためのプライシング戦略
上記職業のかたが、第3章と、第4章を読めば、会計数字にもとづいた利益のでるプライシングになり、自分の値決めに自信がつきます。
費用を固定費と変動費に分ける理由は、第3章にかかれています。
まず最初に、世の中の値下げは、利益がとれるから行われているということが理解する必要があります。
つまり売り上げをみて、経営判断されているわけではないということです。
売上が減ったとしても、利益があがるれば、黒字です。
どうして売りあげが減っても利益が増えるかを理解するために、費用を分解して、固定費と変動費にわけて説明してくれています。
値下げして成功した例として、昔あった100円マクドナルド・ハンバーガーが説明されています。
固定費と変動費の分解し、マクドナルドは、どの部分の利益を削って、どの部分で勝負しようとしていたかがわかります。
また、値下げしてもいいのは、どちらの費用項目かもわかりやすく書かれています。
固定費と変動費が理解でき、値下げしてもいい費用項目がわかれば、「人間そのものが商売するサービス業」での費用と、他の業種の費用の違いもわかります。
第4章では、「人間そのものが商売するサービス業」 では、値下げがダメで、値上げしか生き残る道がないということが、説かれています。
第4章最後に書かれている、値下げ交渉ので相手からいわれたときに切り返す言葉はかっこいいです。
きっとあなたも使ってみようという気持ちにさせてくれます。
第4章で田中さんは、売上からコストを引く従来型の利益を考える数式が、売上至上の考えを招いているといいます。
売上-コスト=利益
なので、その数式から離れ、代わりに、利益を確保するための式を提案しています。
1個の利益(販売単価-仕入れ単価)×販売数量=全体の利益(いわゆる粗利)
利益がどうやって生まれるかという方程式がわかれば、売上が減る恐怖から逃れられますよね。
安売りを続けることをすっぱりやめる決心がつきますよね。
新規顧客をたくさん呼ぶことだけで売上回復が可能と考える単純な戦術はもう限界です。
そこから脱出するには、費用分解の理解と、利益を生むの方程式の2つがカギです。
安売りをやめるのが怖いのに、売上を上げたいと必死な社長さんを救うカギ。
忙しいのに儲からないのをなんとかするカギ。
両方とも、この2つにあると私は考えています。
10-5 『勝間式「利益の方程式」 ─商売は粉もの屋に学べ!─』
勝間さんも 、利益を得る為には価格を1%でも上げようと、著書
のなかで説いています。
利益をとるための方程式を両者ともに提示しているなかで、勝間さんのほうが、先に紹介した田中さんの本より、変数がひとつ多いのです。
田中さんの説く利益の方程式 1個の利益(販売単価-仕入れ単価)×販売数量=全体の利益
勝間さんの説く利益の方程式 (顧客当たり単価-顧客当たり獲得コスト-顧客当たり原価)×顧客数=利益
「顧客当たりの獲得コスト」がどうしてはいっているのかなあとおもって、考えてみました。
わたしなりの考えですが、勝間さんが「供給過多にいまの時代にマーケティングは大切」ということを伝えたかったかたらではないでしょうか。
人口が伸びない日本のなかだけで考えていると、新しい顧客は、結局だれかの失客でしかありません。
だから、プライシングにおいて、会計知識ではなくマーケも大切と方程式にも表して説いているのですね。
勝間さんなりのマーケが大切と説く点で、2つの理由に納得しました。
(1)顧客の声に敏感になれ
顧客獲得コストを究極にゼロにするには、リピーターを増やしロイヤルカスタマーを育ててゆくことと、口コミが発生することにゆきつきます。
会計知識や数字の操作だけで、価格アップを考えている段階では、リピーターになっていただく仕組みや、口コミを得てゆく仕組みづくりがおざなりになり、どうしても「新規客」にばかり目がゆきがちです。
ロイヤルカスタマーでさえ、「既存客」とひとくくりに考えてしまいがちです。
顧客獲得コストに注目し、まず顧客の声を聴いてから出発しようという勝間さんの提案は、利益をもたらすロイヤルカスタマーも大切にする目線をわすれずに全体をみわたせるようになります。
(2)俯瞰的な視点をもつ
顧客獲得コストを極端におさえて利益をとったため、翌期の利益がへってしまった企業の例をあげてくれてます。
それを読むと、自分のビジネスは、顧客獲得コストをどのぐらいの期間で回収するかという思考に向かいます。
いまのコストは次の期の利益になるのか?
長期的な視野で、利益をつくってゆく考えをもつことができます。
単月黒字にこだわる必要もありますが、中小企業の経営者でも、3~5年先の視点をもつ必要があります。
俯瞰的視点も養ってくれる提案なんですね。
高価格化は、利益を得るために行います。
そのために、会計知識だけでもだめだし、心理学の知識だけでもだめだし、利益を削らないように調整する項目にマーケティングの知識も大切という提案だったんですね。
最後に、勝間さんが言ってる「利益は地球資源にも優しい」と説いていた一文を引用して、おきます。
利益を得ることは、私利私欲なのではなく、地球規模に利益をもたらすことなんだと、勇気をもらえます。
P43
もし、より短い時間で高い利益を上げるとこができたら、私たちは低カロリーの食事をもっとゆっくり楽しみながら摂ることができます[略]
つまり、「利益を上げること」は企業にとって必要なだけでなく、私たちが人間らしてく生きるため、充実した人生を送り、そして地球の資源を長持ちさせるためにも、必要な考え方なのです。
10-6 『課金ポイントを変える 利益モデルの方程式』
収益をもたらす課金ポイントを増やしたり変更したりしてサービスを創造しなおし、ビジネスモデル再構築へもう一歩ふみこみたい。
そんなとき、今日ご紹介する本もきっとお役にたてます。
川上昌直著
お役立ちポイントは、
顧客体験から価値を考えるときに時間差を取り入れるという点です。
マイケル・E・ポーターの提唱するバリューチェーンの考えを、顧客体験の時間軸にそってサービス業でもとりいれてみるためのサンプルが図で豊富にしめされています。
大抵は、売り切りモデルです。
この場合、お金をいただくポイントは1回しかありません。
でも、時間軸で、顧客体験をならべてみると、商品を売る前や、売った後など、時間差でお困りごとを解決してゆくことができるタイミングがあり、それぞれ課金できると過程してみる、というアイデアです。
本書で紹介されいるアイデアは、具体的です。
サンプルを参考に、自社についても表をつくりやすいですので、ビジネスモデル再構築なんて難しいということさえ思わずに、手をまずうごかしてやってみようという気になれます。
顧客価値を考えると、自社対顧客という図になりがちで、接触点が1点しかないような図をついあたまに描きがちです。
でも、顧客の体験を時間軸でしめすと、自社がかかわることができる箇所がいつくもあることがみえてきます。
また、自社だけでたりない資源があれば、協力を他社に仰ぐなどの行動もとりやすくなります。
利益を得る為に高価格化を考えるときに、もしただ説明だけでの高価格化に行きづまったら、ビジネスモデルへと一段上に思考をあげて、俯瞰して考え直すことしてみると、やりやすくなります。
ビジネスモデルって、聞いただけで、関わりたくない気持ちがでるかもしれません。
でもそんなこといわずに、本書の図は、まず自社のおかれている業界の顧客になって一緒に考えるときには、「ビジネスモデル」の言葉の意味がわからなくても、役立ちます。
価格を上げたくなっから、どこから手をつけれぱいいか参考にしてください。